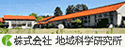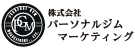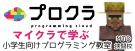- トップページ
- 子育て
- ひとり親家庭(寡婦)支援
- 児童扶養手当 印刷する
現在の位置
児童扶養手当
児童扶養手当
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(高校卒業まで)を養育しているひとり親家庭の父、母又は養育者に支給される手当です。父又は母が重度の障がいの状態にある場合は、ひとり親でなくても支給される場合があります。(1)支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者(政令で定める程度の障がいを有する場合は20歳未満の者)を育てている母子家庭の母若しくは父子家庭の父または養育者に支給されます。・父母が離婚した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が重度の障がいにある児童
※父又は母が障害年金を受け、子の加算がある場合、加算額と児童扶養手当の差額分を受給できる。
・父又は母の生死不明の児童
・父又は母から1年以上遺棄されている児童
・父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・未婚の母の児童
・生まれたときの事情が不明である児童(孤児など)
次のいずれかに該当する場合は支給されません
・受給者又は児童が日本国内に住所を有しないとき
・父又は母が婚姻の届出はしていなくても内縁関係などがあるとき
・児童が里親委託又は児童福祉施設、障害者福祉施設に入所しているとき
(2)支給月
1月、3月、5月、7月、9月、11月・支給月の前月分までの2か月分を支給します。
(3)支給額(令和7年4月現在)
・対象児1人の場合:所得額の区分に応じ、月額46,690円~11,010円の範囲で支給2人目以降:所得額の区分に応じ、月額11,020円~ 5,520円の範囲で加算
※受給者本人の所得が限度額を超えると、一部停止または全部停止となります。
※扶養義務者(同居の家族)の所得が限度額を超えると、全部停止となります。
・毎年8月には現況届の提出が必要です。
(4)所得限度額
所得が下表の額以上の方は、手当の一部または全部が支給停止になります。| 扶養親族等 の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 | ||||
| 全部支給 | 一部支給 | |||||
| 収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | |
| 0人 | 142万円 | 69万円 | 334.3万円 | 208万円 | 372.5万円 | 236万円 |
| 1人 | 190万円 | 107万円 | 385万円 | 246万円 | 420万円 | 274万円 |
| 2人 | 244.3万円 | 145万円 | 432.5万円 | 284万円 | 467.5万円 | 312万円 |
| 3人 | 298.6万円 | 183万円 | 480万円 | 322万円 | 515万円 | 350万円 |
| 4人 | 352.9万円 | 221万円 | 527.5万円 | 360万円 | 562.5万円 | 388万円 |
| 5人 | 401.3万円 | 259万円 | 575万円 | 398万円 | 610万円 | 426万円 |
※扶養義務者とは、申請者本人と同居している直系三親等以内の親族及び兄弟姉妹を指します。複数ある場合は、所得が最も高い方が対象になります。
※1月~9月に申請された方は前々年(10月~12月の場合は前年)の所得が対象になります。
(5)手続き
手当を受けようとする人の請求に基づいて、申請日の翌月分から支給されます。申請の手続きは、本庁舎子育て支援課、挾間地域振興課、湯布院地域振興課の窓口で行うことができます。なお、個別の事情により、必要な書類が異なる場合がありますので、お早めにご相談ください。(6)手当の一部支給停止措置について
「児童扶養手当の受給から5年又は支給要件に該当した月から7年を経過するなどの要件」に該当する受給者は、手当の支給額の2分の1が支給停止となります。ただし、「適用除外の事由」に該当する場合は、届出書を提出することにより減額させません。
※適用除外の事由:就業している、求職活動している、身体上又は精神上の障がいがあるなど
(7)公的年金について
障害者年金以外の公的年金等(※)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。(8)届出
次のような場合は、必ず届出が必要です。届出をしないまま手当を受給した場合は、手当を返還していただくことがありますので、注意してください。| 資格の消滅 | ・婚姻の届出がなくても事実上の婚姻関係と同様の状況となったとき 生活費の援助、頻繁な行き来があるなど ・児童が施設入所又は里親に委託されたとき ・刑務所などに拘禁中の配偶者が出所したとき ・児童を養育しなくなったとき ・遺棄している児童の父又は母から連絡、訪問、送金があったとき |
| 手当の減額 | ・受給者が公的年金を受給するようになったとき(老齢年金・障害年金・遺族年金など) ・児童が公的年金を受給するようになったとき(遺族年金など) ※たとえば母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が遺族厚生年金を受給するようになったときも対象となりますので、届出が必要です。 |
| 養育費の申告 | 児童の父親又は母親から養育費等を受け取っている場合は、その額を申告する必要があります。前年1月から12月までに受け取った養育費等について正しい申告をしてください。 |
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)