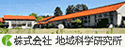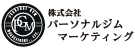- トップページ
- 暮らしの情報
- 年金・保険
- 覚えておきたい国保制度のあれこれ
- 高額療養費・限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証) 印刷する
現在の位置
高額療養費・限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
ただし「限度額適用認定証」の交付を受けた方は医療機関の窓口で支払う金額が高額療養費の自己負担限度額までとなり、窓口での負担が軽減されます。
※70歳未満の方(全員)および70歳以上75歳未満の方は住民税非課税世帯Ⅰ・Ⅱ・現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方に証を交付します。
交付を希望される場合は、入院・外来・調剤等保険医療機関(柔道整復、はり灸、あん摩、マッサージは除く)にかかる前に保険の窓口で申請が必要となります。
※交付できるのは、資格確認書をお持ちの方に限られます。
※マイナ保険証を利用される場合は「限度額適用認定証」の申請手続きをしなくても窓口の負担が軽減されます。(保険税を滞納しているときは、限度額の適用を受けられない場合があります)
高額療養費の申請に必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF)(Excel)
- 国民健康保険の被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ
- 領収書(70歳以上の方は省略可)
- 世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)
- 通帳など受取口座が確認できるもの
- 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)(PDF)(Excel)
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請に必要なもの
- 国民健康保険限度額適用等認定申請書(PDF)(Excel)
- 国民健康保険の被保険者証、資格確認証、資格情報のお知らせ
- 世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)
- 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)(PDF)(Excel)
・91日以上入院したことを証明する領収書・入院証明書等
自己負担限度額(月額)については以下の表の該当する部分をご覧ください。
【70歳未満の方の場合】(月額)
※同一世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が限度額となります。| 所得区分 ※1 | 3回目まで | 4回目以降 ※2 |
|---|---|---|
| (ア)所得金額が901万円を超える | 252,600円+(医療費842,000円を超えた分の1%) | 140,100円 |
| (イ)所得金額が600万円を超え 901万円を超えない | 167,400円+(医療費558,000円を超えた分の1%) | 93,000円 |
| (ウ)所得金額が210万円を超え 600万円を超えない | 80,100円+(医療費267,000円を超えた分の1%) | 44,400円 |
| (エ)所得金額が210万円を超えない (住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 |
| (オ)住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※2 過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
入院したときの食事代はこちらになります。
【70歳以上75歳未満の人の場合】(月額)
外来(個人単位)の限度額を計算後に外来・入院(世帯単位)の限度額を計算します。| 所得区分 | 外来 | 外来+入院(世帯単位) | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ | 課税所得 690万円以上の方 | 252,600円+(医療費-842,000円×1% [4回目以降 140,100円] | ||
| 現役並み所得者Ⅱ | 課税所得 380万円以上の方 | 167,400円+(医療費-558,000円×1% [4回目以降 93,000円] | ||
| 現役並み所得者Ⅰ | 課税所得 145万円以上の方 | 80,100円+(医療費-267,000円×1% [4回目以降 44,400円] | ||
| 一般 | 課税所得 145万円未満の方等 | 18,000円 ※1 | 57,600円 [4回目以降 44,400円] | |
| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者Ⅰ | 住民税非課税世帯 (控除後の所得が0) | 15,000円 | ||
上記の表の灰色で示されている方は限度額適用認定証等が必要となります。
※1 年間(8月~翌7月)の限度額は144,000円です。
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)